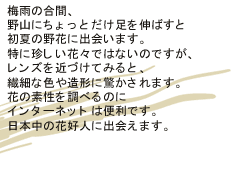|
○西洋アジサイ
西洋アジサイは、早くから七変化する花として珍しがられてきました。品種によっては初めは青だった花が、だんだんに赤に、さらに赤紫色に変わったり、その逆もあるのです。また一株の中でも、枝によって花色が違う品種もあります |
 |
 |
○ノアザミ
山野に生える高さ0.5〜1mの多年草。各地でもっともふつうに見られるアザミで、春から初夏にかけて咲くアザミは本種だけです。茎葉は切れ込み鋭いとげが多く、頭状花は紅紫色で、枝先に上向きにつきます。花は小さな花が多数あつまったものです。 |
 |
 |
○タカトラノオ
タカトラノオは初夏の野山の道ばたを白い花で飾ります。花が茎の先にたれ下がり、その姿がトラ・獣のしっぽに似ているところからこの名があります。 |
 |
|
 |
○どくだみ
独特の臭いがあるために「毒でも入ってるんじゃないか」と思われて「どくだみ」などというかわいそうな名前がついてしまった野草。実際は毒だなんてとんでもなく、薬草として古くからよく知られています。白いかわいい花を咲かせますが、花びらのようにみえる白い部分は本当は葉に近いものだとか。 |
 |
 |
○ニガナ(苦菜)
山地や野原にごく普通に生える多年草です。茎の先端で枝分れし,黄色の頭花をつけます。頭花は普通は5個の舌状花からなりますが、写真のように頭花が大きく,舌状花が7〜11枚のものはハナニガナと呼ばれます。 |
 |
 |
○アカツメクサ
牧草として明治初期に渡来し、全国的に野生化している多年草。畑などのまわりの土手や空き地に多く見られます。シロツメクサとは茎が斜めに立ち上がる点や花の大きさが異なります。ムラサキツメクサとも呼ばれます。 |
 |
|